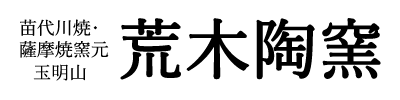2022/12/06 20:02
English:https://shop.arakitoyo.com/blog/2024/08/17/194903

鹿児島に最初に渡来した 朴平意 は苗代川(現:美山)に窯を築き、藩公の庇護奨励のもとに製陶を始めました。
荒木陶窯の当主・荒木秀樹はその末裔で朴家15代です。
薩摩焼の歴史は文禄・慶長の役(1592年~1598年)の際、島津義弘公が朝鮮陶工を連れ帰った事により始まりました。これは千利休の門人であった義弘公の茶道趣味と薩摩藩の産業奨励の為であったと言われています。
慶長3年(1598)渡来した人々は、鹿児島県の串木野(島平)・市来(神之川)・鹿児島市(前之浜)の3箇所に上陸しました。
〇串木野(島平)・・・男女43名、その姓数は18姓で、1姓1族と言われています。
朴(ぱく)・黄(こう)・羅(ら)・燕(えん)・安(あん)・張(ちょう)*鄭(てい)・李(り)卞(べん)・林(りん)・車(しゃ)・朱(しゅ)・盧(ろ)・姜(きょう)・何(か)・陳(ちん)・崔(さい)・丁(てい) その中で、黄・羅・燕は上陸の節に断絶、安・張は琉球へ焼き物師範の為に派遣。
〇市来(神之川)・・・男女10名あまり、その姓は3姓。
申(しん)・金(きん)・盧(ろ)、その後苗代川に合流。
〇鹿児島市(前之浜)・・・男女20名あまり、その姓は李・姜・朱その他は不明。
そのうち李金光は朝鮮国王の親族のため朝鮮に返されました。
鹿児島市高麗町に居住、渡来より71年後の寛文9年(1669年)苗代川へ移住しました。このグループは陶業従事者ではなかったため、陶法指導が行なわれました。